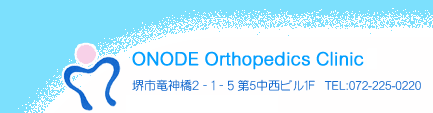2003年の12月に、岡田邦夫先生から、「大阪国際女子マラソンの救護班の医師が足らないので、応援してもらえませんか?」という問い合わせがありました。「私でお役に立つのであれば、参加させていただきます。」とお返事をして・・・。
2004年1月25日(日)
天候は朝から雪がちらつく荒れ模様。数日前から厳しい寒波が訪れていたため、気温はスタート時3.7度と過去最低だったらしい。
12時10分スタートなのだが、午前10時長居競技場の医務室に集合。その時間には、すでに大勢の関係者がせっせと大会の準備に追われていた。廊下を歩けば、有名な選手や監督がジャージ姿でうろうろしている。
救護室では、そのとき医療スタッフのミーティングが行われていた。そこに参加しているのは、医師11名(ドーピングの検査を受け持つ医師2名を含む)と看護師9名、競技場から医務室まで選手を運ぶスタッフが約10名。
それぞれ、選手の後をバスで同行し、リタイアした選手を拾って帰ってくる二組と、競技場でゴール後の不調を訴える選手を受け入れる待機組みとに分けられた。私には、救護室での仕事が割り当てられた。私以外の待機組みの先生は、ベテランの内科の先生、北田仁彦先生と久保とし子先生の2名で、内科的な症状は彼らにお任せして、私は外科的処置が必要な選手を診ることになった。
11時30分過ぎに、バスに乗り込むスタッフが出かけていった後、救護室の設営に入る。ボンボンベットを約20台並べて、それに毛布を敷いていく。使い捨てカイロをいくつも開封し、毛布の中に数個づつ入れて、毛布を暖めておく。脱水症状などを起こした選手に点滴をするためのベットを2台確保、そして足の血豆等の外科的処置が必要な選手のために処置台を2台セッティングする。ベテランの看護師さんたちが、処置、点滴などに必要な物品を手際よく並べてくれた。12時10分のスタートを見送り、そこでお弁当をいただく。待機組みは、ゴールするまで約2時間半は仕事がない。しばしの休憩である。設置してあるテレビでレースを見守る。途中でリタイアした人が、病院に搬入されたとの連絡を受けたが、その人もすぐに回復したらしく一同ホッと胸をなでおろす。緊急の事態に備えて、カウンターショックなどの心肺蘇生装置をバス等に積み込んである。
ベテランの先生に聞いたが、大阪国際女子マラソンでは、まだそれらの装置を使用したことはないそうである。でも、いつ何時そういう事態が発生してもおかしくないので、やはりドキドキする。スタートから2時間を過ぎ、モニターでトップの選手がボツボツ競技場に帰ってくる。今回のトップは、岡山天満屋の坂本直子選手、2位の千葉真子選手をぶっちぎってダントツのトップである。でも、タイム自体は結構スローペースだった。寒さのせいだろうか?目の前で、ガッツポーズの坂本選手がゴールテープをきった。感動ものだ!!こんな良い席で、見せていただくなんて!!
しばらくして、後続の選手がどんどんゴールしてくる。上位でゴールしてくる選手は、やはりまだ余力があるのか倒れこむような選手はほとんどいない。2時間40分を越えるころから、ゴールで倒れこむ選手、ゴールと同時に嘔吐する選手が出てくる。彼らが、担架で次々に救護室に運び込まれてくる。これだけ走ってきたにもかかわらず、選手の身体は冷え切っており、血管が収縮しているのと脱水で脈が取れない。意識状態の確認をして、脈拍、血圧などのいわゆるバイタルサインのチェックを行う。氷のように冷え切った手足を、使い捨てカイロを握らせたり、脇の下にはさんだりし、毛布でくるんで暖める。少し暖めたポカリスエットをゆっくり少量ずつ飲ます。身体が温まってくると、みんな少しずつ落ち着きを取り戻してくる。中には、胃痙攣を起こして、嘔吐し続けるもの・・・点滴。足の痙攣を起こすもの・・・看護婦さんに他動的にストレッチをさせてもらう。足にカイロを貼り付ける。過換気症候群で意識朦朧状態の選手・・・点滴とペーパーバックによる再呼吸をさせる。
私の出番 レース途中で転倒して、肩を打撲し手があがらない選手がきた。幸い、骨折や腱板の損傷らしい所見がなく、打撲と判断してシップ処置。もう一名は転倒で、肘から出血している。これも、いわゆる擦過傷で、消毒処置をして終了。大会事務局から電話が入り、スタンドで落ちた子供がいるとのこと。やってきたのは、4歳くらいのこどもさん。おでこに大きなたんこぶを作っている。意識もはっきりしているので、氷でのアイシングをする。10分ほどで、落ち着いたので帰宅させる。
外科的な処置は、あまりなく、いつもは足の裏の血豆の処置などの選手が多数くるらしいが、今回は1選手が来ただけで、他はなかった。他の先生方から、「先生は魔よけみたいな存在やね。けが人が今年は少なかったわ。」と言われたが、喜んで良いのか複雑な気分だった。
その他の感想
選手たちが搬入された時、はいているシューズを脱がすが、みんな靴紐が解けないようにいろんな工夫をしている。結び目をもう一度結ぶのは当たり前で、くくった紐を、もう一度前のほうの紐のクロスしている部分にくくりつけたり、中には靴紐をパズルのように組み込んでいる選手もいた。この紐を解くのが一苦労。この、紐のきつさに泣いていた選手もいた。走り出してからすぐに痛くなったが、それが気になって走れなったとの事。ちょっとしたことが、長丁場にはこたえるのだろう。脱がせた靴は、どの選手の靴も羽のように軽い。これらの靴をはいて走るのであれば、はだしの感覚で走れるのでは・・・。
すべての選手が、低体温に泣かされている。防寒対策としての手袋や、アームウォーマーのようなものをみんなはめているが、給水やスポンジをもらうことによって、それがぬれる。ゴール後の手袋などは、びちゃびちゃにぬれている。これが、体温を奪う原因の一つになっているのであろう。ほとんどの選手がゴールしたころに、バス組みの救護班のスタッフが帰ってきて、残りの選手の世話を一緒にしてくれた。ここで、私の仕事はお役ごめんになった。
マラソン競技の成功の影には、たくさんのボランティアの活動があることを、再認識しましたし、今回私もそこに参加させていただいたことを誇りに思います。
選手の皆さん、救護班の先生方、看護師さんたち、その他のスタッフの皆さん、影で支えてくださった大勢のボランティアスタッフの皆さん、お疲れ様でした。そして、感動をありがとう!!
|

役割を終えて、看板の前で記念撮影。

スタート直後、気温3.7度、曇り空。

競技場2週目で、早くも先頭集団と後続組みに分かれる。

救護室の設営に入る。ボンボンベットと、毛布の用意。使い捨てカイロを毛布の間に敷いていく。

坂本選手のゴールを目の前で見る。
感動した!!

順次、選手が運び込まれる。
選手の身体は、冷え切っている。

スタッフの先生方、看護師さんたちと記念撮影。
|
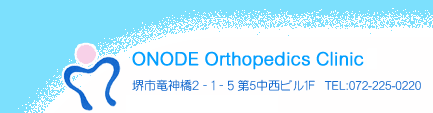
![]()